社会福祉法人会計の実務
会計基準省令に準拠
社会福祉法人の会計担当、
経営に携わる方々に必須の通信教育講座です!

〒107-0062 東京都港区南青山2-11-17 第一法規ビル
閉じる
会計基準省令に準拠
社会福祉法人の会計担当、
経営に携わる方々に必須の通信教育講座です!
本講座は、主に社会福祉法人の会計担当者・管理者の方々を対象とした通信講座です。
「社会福祉法人会計基準」は、平成28年3月より厚生労働省令として新たに制定され、
その後一部改正が加えられて、平成29年度より適用されることになりました。
その新しい「社会福祉法人会計基準」に準拠した会計処理実務の基本的な仕組みを、わかりやすく説明しています。
STEP1受講申し込み

STEP2教材お届け

STEP3学習スタート

STEP4添削指導

STEP5受講終了

あなたのペースで、あなたにあった学び方
本講座では、社会福祉法人会計の基礎的な知識を取得し、日常業務に応用できるよう体系的に学習していきます。
独学でもしっかり理解できるよう、私たち講師と事務局がサポートいたします。

私の長年の業務経験に基づきわかりやすく丁寧に説明し、皆さんが社会福祉法人会計を理解できるよう、全力でサポートします。
私の趣味であるウォーキング同様、一歩一歩着実に進みましょう。
決してあせることはありません。一緒に歩んでいきましょう!
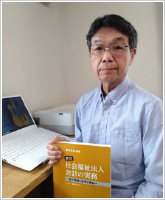
現在、山下清画伯が在園していた障害児入所施設「八幡学園」の事務長として従事する傍ら、本講座の添削に携わっています。
何かを始める、それをコツコツ続ける、いつか自分の身に付いたものの大きさに気づきます。
好奇心と勇気を持って何かを始め、諦めずに続けてほしいと思います。
詳しくはこちらをご覧ください
学習の手引
B5判(1冊)
学習する前にお読みいただき、ご自身の学習計画を立案ください。
テキスト
A4判(1冊)
簿記の基礎概念から複式簿記の原理、伝票の作成、勘定科目の説明、決算まで、具体的な記入例を揚げて説明しています。
解答の手引き
A4判(1冊)
難しいと思われる箇所や間違えやすい箇所、ご質問が多く寄せられる箇所について、正解へのヒントをまとめています。
添削問題集 A4判(1冊)
解答用紙
B4判(1冊・6回分)
月1回のペースを目安にご提出ください。
模範解答
A4判(6回分)
添削指導後の各回の解答用紙と一緒にお送りいたします。
仕訳伝票
B6判(2冊)
添削問題の解答に取組むときに用います。
質問用紙
A4判(1枚)
受講期間中(修了証書受領後含む)は、本講座の内容に関する質問にお答えします。
複数回のご質問も可能です。コピーの上ご利用ください。
関係資料
B5判(1冊)
講座に関する厚生労働省令(新会計基準)等を掲載しています。
必要に応じてご参照ください。
修了証書 全6回の添削問題を一定の基準で修了されますと、「修了証書」が交付されます。